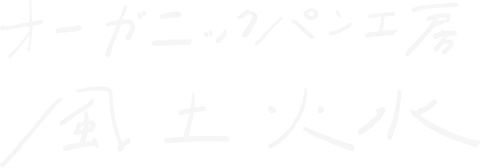

千葉県出身の梅澤シェフがパン職人としての道を歩み始めたのは、専門学校を卒業後に就職した、首都圏に拠点を持つベーカリーから。複数店舗を手がける企業だったため、勤務先は店舗ではなく、”セントラルキッチン”。そこで14年にわたりパンを焼き続けた。
とにかくパンを作ることが好きだったんです。
セントラルキッチンと言っても、手仕事が中心の現場。ひたすらパン作りと向き合う日々が続いた。
もともと独立を前提に修行をしていたという梅澤シェフ。資金、技術、タイミングを見極めながら、満を持して独立。場所への執着はなかったため全国どこへでも物件探しに回ったが、最終的にパン屋を構えたのは、生まれ育った地元・千葉県流山市だった。選んだ立地は、あえて商業エリアではなく住宅街の中。
「ついでに買うパン」じゃなくて、「わざわざ来てもらうパン屋」にしたかった。
メインに据えたのはハード系のパン。一方で、食パンやクロワッサン、メロンパンといった日常に寄り添うパンも多くの人に親しまれ、地域の暮らしに溶け込むベーカリーとして、9年半にわたり営業を続けてきた。
独立を果たし、日々パンを焼く中で、梅澤シェフの中には次第に「もっと深くパンと向き合いたい」という思いが芽生えていった。
パン作りの工程や在り方を見つめ直す中で、強く惹かれるようになったのが“薪窯”という焼成方法だった。電気やガスとは異なり、薪をくべ、火を起こし、窯と対話しながら焼き上げるパン。

理屈というより、感覚的に「これはやってみたい」と思ったんです。
薪で焼いたパンには、言葉にしきれない魅力があると感じていました。
「薪窯でパンを焼いてみたい」ーー
その思いが強くなり、もう一度、全国規模での物件探しが始まった。


薪窯を前提とした環境探しは簡単ではなかったが、そんな中で出会ったのが、アグリシステム、そしてベーカリー風土火水だった。

ちょうどその頃、風土火水の前任のシェフが退社予定で、新たに「パン職人」を探していると言うタイミングだった。
2023年開催のオーガニックビレッジでの出会いをきっかけに、話は一気に進む。十勝はこれまで縁のなかった土地だったが、実際に訪れ、暮らしを想像する中で、その印象は大きく変わった。
帯広が心地良いと感じました。
生活に不便はなく、子育て環境も整っている。
ここなら、家族と一緒に安心して暮らしていけると感じました。
2024年2月4日、十勝地方を一晩で100cmを越える災害級の大雪が降った日。運良く、その前日に引っ越しを終えることができた。忘れられない十勝でのスタートだ。

風土火水に勤める以前は、材料が国産か、そうでないかには強いこだわりはなかった。
あくまで「味が基準」。それが一貫した考えだったという。
しかし十勝に来て、麦畑を見て、生産者と話す中で、意識は確実に変わっていく。
生産者とつながることって、これまではなかったんですよね。
アグリシステムの取り組みの中で、畑にも通う回数が増えた。
誰が、どんな畑で、どんな小麦を育てているのか。それを知ったうえで焼くパンは、これまでとは違う感触を持ちはじめている。
4月から働き始め、最初は前任のシェフに教えてもらいながら、薪窯を扱ってきた。1人で焼くようになり、段々とリズムのできてきた秋口に事件は起こる。
なんと、肝心の薪窯が、修繕中に壊れてしまうというハプニングが。
3ヶ月半、電気オーブンでパンを作る事という苦い経験にもなったが、改めて薪窯の火通りの良さ、焼き上がるパンの表情や味の違いを再度認識することができる良い機会となった。
風土火水はなるべくエネルギーを使わないように考えられたベーカリーだ。
生地を作るのも食パン以外はミキサーではなく、手ごね。酵母も自家培養酵母。
IBEテクノ株式会社製のπウォーターを使い、素材も極力シンプルに。
小麦粉をはじめ、ドライフルーツやナッツ類など、ほとんどが有機JAS認証された食材を使用している。

電気を使わないことは、災害などがあって、電気が止まったとしても、パンが焼けるということ。
その核となるのが「薪窯」の存在だ。
シェフの出勤は深夜2時。そこから薪をくべ、パン作りがスタートする。パチパチという薪のはぜる音を聞きながら、前日から冷蔵発酵させておいたパンを成形、焼く準備を進めていく。

薪を足し、温度を確認し、「ここ」というタイミングを見極めて、火をくべるのをやめる。そこからは、徐々に下がっていく薪窯の温度を計りながら、その日のパンを順番に焼いていく。
すべてを自分の手と感覚で作り上げていく風土火水のパン作り。
ここは、挑戦できる環境だと思っています。
今が完成形というわけでもないですし、常に進化・変化していくベーカリーです。

薪で焼くこと。
土地の小麦を使うこと。
生産者の顔が見えること。
シェフにとって日常となった日々こそが、風土火水のパンに特別な価値を与えている。
取材・文(2026年2月作成)/外山暁子 撮影/いくのめぐみ